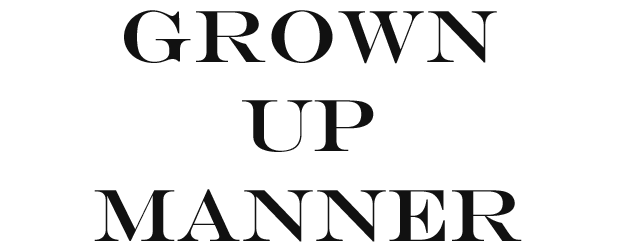その「ちょっと面倒」を、ChatGPTが代わりにこなす時代
「この文章、あとで整えておこう」「メールの返信、あとでまとめて…」
そんなちょっとした後回しが積み重なって、気づけば残業。
ChatGPTは、そうした細かいタスクの山をさっと片付けてくれる頼もしい存在です。
もともとChatGPTは、OpenAIが開発したAIチャットツール。自然な文章を生成したり、要点をまとめたり、質問に即答したり。まるで賢い秘書のように動いてくれるのが魅力です。
最大の特徴は、質問の意図や背景を読み取る「文脈理解力」にあります。ちょっと曖昧な指示でも、そこから最適解を導き出そうと働いてくれるのです。
日々の業務の中で、「書く」「考える」「まとめる」といった作業が少しでも多いなら、一度使ってみる価値は大いにあります。
ChatGPTを業務にどう使う?
たとえば、打ち合わせメモをもとに議事録を起こすとき。箇条書きのメモを渡せば、ChatGPTは数秒で読むに耐える文章にまとめてくれます。
ただ整形するだけではありません。話の流れや重点を考慮して、自然な構成に仕立ててくれるのが心強いポイントです。
メールの下書きにも活用できます。返信が難しい内容も、背景を伝えれば角の立たない表現で提案してくれるので、メールに悩む時間もぐっと減ります。
また、企画書のタイトル案やキャッチコピーのたたき台を出してもらうなど、発想のきっかけ作りにも使えます。
さらには、業務マニュアルや社内FAQの初稿作成にも力を発揮します。構成をざっくり伝えれば、それに沿ったドラフトがすぐに手元に届く感覚です。
他にも、英語メールの翻訳やトーン調整、作業リストの分類整理など、小さな業務サポートも数えきれないほど。
大がかりな導入は不要で、ブラウザがあれば使える点も魅力です。無料版でもある程度使えますので、まずは試してみるのがおすすめです。
導入前に押さえておきたいポイント
ただし、便利だからといって、すべてを任せてしまうのは少し危険。
ChatGPTの回答は、過去の情報をもとに生成されているため、最新の情報が反映されていないこともあります。また、事実のように見えても実在しない内容が含まれるケースも。
たとえば、「社内でこの制度って導入されてる?」と聞いて、ありそうな説明をしてくれることもありますが、それが本当とは限りません。必ず人の目で確認し、情報の裏をとる習慣を持ちたいところです。
また、入力した内容が外部に漏れる心配はないか──これもよくある不安です。OpenAIでは、学習に使わない設定も用意されていますが、完全な機密保持を保証するものではありません。
そのため、個人情報や社内の機密情報を入力しないルールづくりは必要不可欠です。チームで使う場合は、ガイドラインの整備も視野に入れましょう。
加えて、ChatGPTはあくまでも「補助役」。判断が必要な場面では、必ず人が最終確認を行う仕組みがあると安心です。
たとえば、「この提案でクライアントは納得するだろうか?」といった、感情や関係性を加味した判断は、AIではまだ完全には担えません。
こうしたリスクを理解した上で、少しずつ業務に取り入れていくと、無理なく効率化を進められるでしょう。